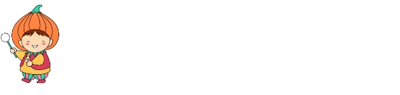水害は他人事と考えている方はいませんか。9月21日には、北海道でも線状降水帯が初めて観測されました。このように、水害のリスクは、過去の洪水をみても、近年の異常気象からも、栄東地区においてもそのリスクを常に意識していなければなりません。
10月5日、水害を意識した住民主体の避難所運営訓練を栄東小学校で開催しました。これは、北海道胆振東部地震の教訓を生かし、住民自らが避難所を設置し、避難者を受け入れるというシミュレーション訓練です。今回は、連合町内会の第4分区の町内会と連町役員、消防団の40名が設置者となり、栄東小学校に避難所を設営し、第1・2・3分区の町内会会員が避難者となって訓練を行いました。
最初、駆け付けた札幌市職員が暗証番号を入力して、学校を開錠するというところから訓練をスタートし、4階の備蓄庫から非常食や防災用品を体育館に運び、東側玄関に受付を設け、体調不良者を検温して受け付ける臨時受付も設けました。体育館では、避難者を疑似家族に設定し、1人用、2人用から5人用まで避難スペースをつくり、みなさんに割り当てるなどの実践さながらの訓練です。
また、避難スペースに落ち着いてからは、避難者に映像を使って栄東地区を取り巻く水害リスクや避難時の対応、情報収集などのミニ講座で、いざというときの対応を学びました。
途中、非常食を加熱剤で温めた温かい食事の試食も行い、東区職員からは、備蓄物資についての説明を受け、実際の重さの体験などを行いました。
最後は、備蓄物資班が仕分けした、配給の非常食を受け取り家路につきました。災害はいつ起こるかわかりません。こうした地道な体験が、万が一の災害時、迅速に地域住民が自ら自分たちの命を守るという行動につながっていくことでしょう。



説明をする東区役所の平岡係長










に応じてスペースを割り当て

栄東地区独自のブルーシート方式








説明する東区役所の平岡係長

東消防署・栄出張所の中島係長